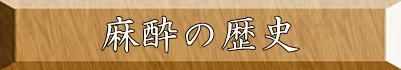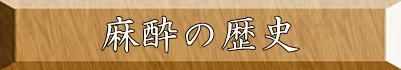| ���E |
���{ |
| �N |
���� |
�l�A�c�� |
���l |
�N |
���� |
�l�A�c�� |
���l |
|
���ɂƍÖ���p�̂���l�x���e�Ƃ���������҂ɗ^���Ė��ɉ��Ɏ�p���s���� |
�M���V���̈�_�A�X�N���s�A�X |
|
|
|
|
|
|
���ЁA�q���X�A�}���_���Q�Ȃǂ��C�ȂɐZ���č�����Ö��C�Ȃ�p���Ēɂ݂�a�炰�� |
Hippocrates / Galen |
|
|
|
|
|
| 1540 |
�G�[�e���̍����ɐ��� |
V. Cordus |
 �h�C�c�̈�t �h�C�c�̈�t |
|
|
|
|
|
|
|
|
1689 |
�\�ʖ������ɓe�O�p���s�� |
���� ���� |
���� |
| 1771 |
�_�f�̔��� |
J. Priestley / K. W. Scheele |
 / /  |
|
|
|
|
| 1772 |
���_�����f�̔��� |
J. Priestley |
|
|
|
|
|
| 1779 |
���_�����f�̖�����p�����A�C�Ɩ��Â��� |
H. Davy |
 |
|
|
|
|
| 1804 |
���Ђ��烂���q�l��P�� |
F. W. A. Sertüner |
 |
1804 |
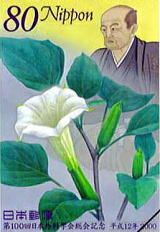 |
�@�u�ʐ�U�v�ɂ��S�g�������ɓ����̎�p�ɐ��� |
|
�؉� �F |
|
| 1831 |
�N�����z�����̑n�� |
J. V. Liebig / E. Soubeiran / S. Guthrie |
���ꂼ�ꖳ�W�ɓ��N�ɑn�� |
|
|
|
|
| 1842 |
�G�[�e�������ɂ�锲������ |
W. E. Clarke |
 |
|
|
|
|
| �G�[�e�������ɂ����ᎂ̓E�o�ɐ��� |
C.W. Long |
 |
|
|
|
|
| 1844 |
���g�̔����ɏC���g�p�����ɂ� |
H. Wells |
 ���Ȉ�t ���Ȉ�t |
|
|
|
|
| 1845 |
�C�K�X�̌��J�����Ɏ��s |
H. Wells |
|
|
|
|
|
| 1846 |
 |
�@�G�[�e���̌��J���� |
|
W. T. G. Morton |
 ���Ȉ�t ���Ȉ�t |
|
|
|
|
| ���� (anesyhesia) �Ƃ����p�ꂪ���߂ėp������ |
O. W. Holmes |
W. T. G. Morton �̗F�l���ނ̎��������Ĕ��� |
|
|
|
|
| 1847 |
�N�����z�����̗Տ����p�J�n |
J. Y. Simpson |
 �G�W���o����w �G�W���o����w |
|
|
|
|
| �G�[�e�������ɂ�閳�ɕ��؍s���� |
J. Y. Simpson |
|
|
|
|
|
| �ŏ��̖����Ȑ���a�� |
J. Snow |
 �����h�� �����h�� |
|
|
|
|
| �G�[�e���̒����������L�q |
N. Pirogoff |
���V�A |
|
|
|
|
|
|
|
|
1850 |
�u�ϐ����l�v�ɂ͂��߂āf�����f�Ƃ��������������� |
���c ���� |
|
| 1853 |
Victoria �����̑攪�q�ALeopord���q�̏o�Y�ɍۂ��āA�N�����z����������p�������ɕ����s�����B���Ԉ�ʂɖ��ɕ����������_�@�ƂȂ� |
J. Snow |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1855 |
�{�M���̃G�[�e���������s���� |
���c ���� |
|
| 1857 |
Victoria �����̑��q�ABeatrice�����̏o�Y�ɍۂ��āA�N�����z����������p�������ɕ����s���� |
J. Snow |
|
1857 |
�N�����z���������Љ��� |
P. von Meerdevoort |
�I�����_�C�R�R�� |
| 1860 |
�R�J�C���̐��� |
A. Niemann |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1861 |
�{�M���̃N�����z���������s���� |
�ɓ� ���p |
|
| 1862 |
�R�J�C���̐�S���ɑ��閃�����̕� |
Schroff |
|
|
|
|
|
| 1864 |
�o���r�^�[���_�̔��� |
von Baeyer |
|
|
|
|
|
| 1868 |
�C�K�X��20���̎_�f�p |
E. W. Andrews |
 �V�J�S�̊O�Ȉ� �V�J�S�̊O�Ȉ� |
|
|
|
|
| 1869 |
�C�Ǔ��}�ǁi�o�C�ǐ؊J���j |
Trendelenburg |
|
|
|
|
|
| �g���N���[���G�`�����̔��� |
Fischer |
 ���w�� ���w�� |
|
|
|
|
| 1875 |
�����N�����[���̐Ò��ɂ�薃���ɐ��� |
Oré |
|
|
|
|
|
| 1876 |
�C�[�G�[�e���������n�߂� |
J. Clover |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1878 |
�{�M�ɏ��߂ăR�J�C�����A������� |
���X�x���� |
�a�@�p���{�i |
| 1880 |
�o���C�Ǒ}�ǂ̒� |
W. MackEwen |
 �O���X�S�[ �O���X�S�[ |
|
|
|
|
| 1881 |
�N�����z���������ɐ旧�������q�l�ɂ��O������s�� |
A. Crombll |
�C���h |
|
|
|
|
| 1884 |
�R�J�C���Տ����p��\�ʖ����ɗp���� |
C. Koller |
|
|
|
|
|
| 1885 |
�R�J�C���̒��˂ɂ��_�o�u���b�N�@�ƕ\�ʖ����@��� |
Halsted |
 |
1885 |
�R�J�C���̗Տ��g�p�J�n�i�����j |
|
|
| �d���O�����ɐ��� |
L. Corning |
|
�ɖ� �t�B |
|
|
|
|
|
1887 |
��������G�t�F�h�����̒P���ɐ��� |
���䒷�`�� |
|
| 1889 |
�`�B��������ʂɍL�����p |
M. Oberst |
|
|
|
|
|
| 1891 |
�g���|�R�J�C���̕��� |
Giesel |
|
1891 |
�č�����C�̋z����������A�蔲���ɗp���� |
�ЎR �֕F |
|
| 1893 |
London Society of Anaesthetists���� |
|
 |
|
|
|
|
| 1894 |
�R�J�C���ɋǏ�������̖���^���� |
k. L. Schleich |
|
|
|
|
|
| �N���[���G�`�����z�����������ɐ��� |
Carlson |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1895 |
�C�K�X�����������A�� |
�_�� ���� |
|
|
|
|
|
1896 |
���Ȋw��Ő_���̖�������g���C�̋z�������s���� |
�ɑ�M�� |
|
| 1897 |
�R�J�C���n�t�ɃG�s�l�t������������Ƌz����x�����A�������Ԃ��������鎖�\ |
H. Braun |
 |
|
|
|
|
| 1899 |
�ҒŖ����̗Տ����p |
A. Bier |
�L�[����w |
|
|
|
|
|
|
|
|
1900 |
�A�h���i�����̒��o�ɐ����i�z�����������j |
������g�� |
|
| 1901 |
�G�[�e���_�H���N�����n�܂� |
P. Sudeck |
|
1901 |
�{�M���̐ҒŖ����̏Ǘ�y�ѐ��E���̃����q�l�����������^ |
�k�� ����Y |
���� |
| 1902 |
�d�C�����ɐ��� |
Le Duc & Rouxeau |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1903 |
�{�M�ɍd���O�����Љ��� |
|
|
| 1904 |
Buchanan��New York Medical College �ŕč��ŏ��߂Ă̖����w����(College)�ɏA�C |
|
 |
|
|
|
|
| 1905 |
���_�v���J�C���̍��� |
A. Einhorn |
 |
|
|
|
|
| Long island Society of anesthetists �ݗ� |
Erdmann |
 |
|
|
|
|
| 1909 |
�v���J�C���Ö����˂ɂ��Ǐ��������J�n |
A. Bier |
|
1909 |
�{�M�ōd���O��������p�ɉ��p����� |
|
|
| 1910 |
�K�X�̍Čċz�@������ |
Gatch |
|
|
|
|
|
| 1910 |
�d�C�������ɑ��̐ؒf�ɐ��� |
L. Rovinovitch |
|
|
|
|
|
| 1911 |
Long island Society of anesthetists �� New York Society of anesthetists
�ƂȂ� |
|
|
|
|
|
|
| �����I�Čċz�@���� |
McKesson |
|
|
|
|
|
| 1913 |
�l�̖���������̂ɕK�v�ȃG�[�e�����C�̒��͂�50mmHg�ƂȂ邱�Ƃ����߂� |
C. Connell |
|
|
|
|
|
| 1914 |
�G��American Journal of Anesthesia and Analgesia �� American Journal of
Surgery �̋G�����s�̗Վ������Ƃ��đn�� |
|
 |
|
|
|
|
| 1918 |
�G�`�����̖�����p���� |
A. B. Luckhert |
|
|
|
|
|
| 1919 |
National Anesthesia research Society �ݗ� |
McMechan |
 |
|
|
|
|
| 1920 |
�G�[�e�������[�x���S���ɕ��� |
Guedel |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1921 |
�u�A���R�[���ɂ��o�Ö��I�_�H�����@�v�i�ƕ��j���\ |
���쏬�l�Y |
���k�鍑��w�����O�� |
| 1922 |
�G�� Current Researches in Anesthesia and Analgesia �n�� |
|
|
|
|
|
|
| �A�Z�`�����̖�����p����� |
H. Wieland & C. J. Gauss |
|
|
|
|
|
| 1923 |
�G�`�����Տ����p |
A. B. Luckhert |
|
|
|
|
|
| �č����̖����Ȍ��C��(Iowa)�a�� |
Mary A. Ross, M.D. |
 |
|
|
|
|
| �G�� British Journal of Anaesthesia �n�� |
|
 |
|
|
|
|
| 1924 |
National Anesthesia research Society �� International Anesthesia research
Society (IARS) �ƂȂ� |
|
 |
|
|
|
|
| Mayo Clinic �����ȑn�� |
Dr. John S. Lundy |
|
|
|
|
|
| 1926 |
�G��American Journal of Anesthesia and Analgesia �p�� |
|
 |
|
|
|
|
| 1927 |
University of Wisconsin �ŕč����̖����w�S���̑�w����(University)�a�� |
Dr. Ralph M. Waters |
 |
|
|
|
|
| Anesthetist's travel club �ݗ� |
|
|
|
|
|
|
| 1928 |
�ӖړI�o�@�C�Ǔ��}�ǂy |
Magill |
|
|
|
|
|
| 1929 |
�W�u�J�C���J�� |
|
|
|
|
|
|
| 1930 |
�e�g���J�C���J�� |
|
|
|
|
|
|
| 1932 |
Association of Anesthetists of Great Britain and Irland (AAGBI) �ݗ� |
|
 |
|
|
|
|
| 1933 |
�T�C�N���v���y�������̗Տ����p |
R. Waters & E. A. Rosenstein |
|
|
|
|
|
| 1934 |
�`�I�y���^�[��(Pentothal)��p���Ė��������� |
J. S. Lundy |
|
1934 |
���Ȗ����w�u�����݂����� |
���{���Ȉ�w���w�Z |
|
| 1935 |
New York �� Bellevue Hospital �Ŗ����Ȑݗ� |
Rovenstin |
 |
|
|
|
|
| 1936 |
New York Society of anesthetists �� American Society of Anesthetists �ƂȂ� |
|
 |
|
|
|
|
| 1937 |
���̔N�o�ł��ꂽ Inhalation Anesthesia �̒��ŁA�G�[�e���̖����[�x��4���ɕ������ |
Guedel |
 |
|
|
|
|
| 1938 |
The American Board of Anesthesiology �ݗ� |
|
 |
1938 |
�u���[���[�ɉ�����O�Ȗ����̋ߋ��v�̒��ŕč��̖����̌���������A�C�Ǔ������ɂ��Ă��ڏq����Ă��邪�A���O�̍���ɂ�蕁�y���Ȃ����� |
�i�]�叕 |
���R�R��w�Z�O�Ȋw���� |
| 1940 |
�G�� Anesthesiology �n�� |
|
 |
|
|
|
|
| �����ҒŖ����@�̔��\ |
W. T. Lemmon |
 �t�B���f���t�B�A �t�B���f���t�B�A |
|
|
|
|
|
|
|
|
1941 |
�W�u�J�C���̍���d�t��p���̈ʂɂ���Ė����̃��x����C�ӂɕς�����@�\ |
�p���G�E�֓��� |
������w |
|
|
|
|
�����m�푈�J�� |
|
|
| 1942 |
�N���[�����S�g�����ɗp������ |
H. Griffith & E. Johnson |
�����g���I�[�� |
|
|
|
|
| 1943 |
���h�J�C������ |
Löfgen & Lundgvist |
|
|
|
|
|
| �}�b�L���g�b�V���^�A�����̔��� |
Mackintosh |
 |
|
|
|
|
| 1945 |
American Society of Anesthetists �� American Society of Anesthesiologists
�ƂȂ� |
|
 |
1945 |
�����m�푈�J��I�� |
|
|
| 1946 |
�G�� Anaesthesia �n�� |
|
|
|
|
|
|
| 1947 |
���h�J�C���Տ����p |
Gordh |
|
|
|
|
|
| 1948 |
�ጌ��������S���O�Ȏ�p�ɉ��p |
Griffith & Gillies |
|
|
|
|
|
| 1949 |
�T�N�V�j���R�����̋ؒo�ɍ�p���� |
A. P. Philips |
|
|
|
|
|
| 1950 |
��̉���S���O�Ȏ�p�ɉ��p |
W. G. Bigelow |
|
1950 |
���ĘA����w�ҋ��c��J�Â���� |
Saklad���m�痈�� |
���{�̖����Ȉオ��㏉�߂ĕč��̐i�����ɐG��� |
| 1951 |
�T�N�V�j���R�����Տ����p |
von Dardel & Mayerhofer |
|
1951 |
�`�I�y���^�[���i�g���E�����Y������ |
�c�Ӑ��� |
���{�i�[���̖��O�Ŏs�� |
|
�A�����j�A�̒��ڎ_���@�ɂ��C�̎��������J�n |
���a�d�H�� |
|
| 1952 |
�G�� der Anaesthetist �n�� |
|
|
1952 |
���{���̖����w�u�����J�݂��ꂽ |
������w��w�� |
|
|
|
�T�N�V�j���R�����g�p����� |
|
|
|
|
�G���@�u�����v�@�n�� |
|
|
| 1953 |
Association of University Anesthetists �ݗ� |
|
|
|
|
|
|
| Residency Review Committee in Anesthesiology �ݗ� |
|
|
|
|
|
|
| 1954 |
�G�� Canadian Anaesthetist's Society Journal �n�� |
|
|
1954 |
��P����{�����w���J�� |
|
�L����� |
| Anaesthetists travel Club �� Academy of Anesthesiology �ƂȂ� |
|
|
�G���u�����v�����{�����Ȋw��@�֎��ƂȂ� |
|
|
|
|
|
|
1955 |
�{�M�ɂ�����͂��߂Ă̏C�����̔� |
�ʕ{���w�� |
|
| 1956 |
���s�o�J�C������ |
Ekstam & Egner |
|
1956 |
���a�d�H���C�̐����̔��J�n |
���a�d�H�� |
|
| �n���^������ |
C. W. Sucking |
|
|
| 1957 |
���s�o�J�C���Տ����p |
Dhunér |
|
1957 |
�n���^�������{�ɏЉ��� |
|
|
| �G�� Survey of Anesthesiology �n�� |
|
|
|
|
| �G�� Acta Anesthesiologica Scandinavica �n�� |
|
|
|
|
| �G�� Current reseaches in Anesthesia and Analgesia �� Anesthesia and Analgesia,
Current Reseaches �ƂȂ� |
|
|
|
|
| 1958 |
Audio Digest Anesthesiology �̏����^ |
|
|
|
|
|
|
| 1959 |
���g�L�V�t�������Տ����� |
von Pouznak & J. F. Artusio |
 �R�[�l����w �R�[�l����w |
|
|
|
|
| NLA �Љ��� |
De Castro & P. Mundeleer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1962 |
�����w���㐧�x���� |
|
|
| 1963 |
�u�s�o�J�C���Տ����p |
Widman |
|
1963 |
��1����{�����w����w����F�莎���{�s |
|
|
| �G���t���������� |
R. C. Terrrell |
 |
|
|
| �h���y���h�[������ |
P. A. J. Jansen |
|
|
|
| �������M�̔��� |
|
|
|
|
| 1964 |
�q�g�ɂ�����MAC���u�畆�؊J�ɑ�50���̊��҂��̓����������_�̔x�E���ŏ�������Z�x�v�ƒ�` |
Saidman & Eager |
 |
1964 |
���g�L�V�t�������Տ��g�p�J�n |
|
|
| 1965 |
�C�\�t���������� |
R. C. Terrell |
 |
1965 |
���������a�@�J�� |
|
|
| �t�F���^�j������ |
P. A. J. Jansen |
|
|
|
| �P�^�~���J�� |
E. F. Domino & G. Corssen |
|
|
|
| 1966 |
�G���t�������K�����O |
Virtue |
 |
|
|
|
|
| �f�X�t��������������� |
R. C. Terrell |
|
|
|
|
|
| 1967 |
�L���p���N���j�E���Տ����p |
|
|
|
|
|
|
| ARDS�̒� |
|
|
|
|
|
|
| PEEP���p |
|
|
|
|
|
|
| 1968 |
�Z�{�t��������������� |
Regan |
 |
|
|
|
|
| society of Academic Anesthesia Chairmen �ݗ� |
|
|
|
|
|
|
| 1969 |
�S����p�ɂ������ʃ����t�B�������̎g�p���L�߂�_�@�ƂȂ�_���\ |
Lowenstein |
 |
|
|
|
|
| 1971 |
�Z�{�t�������̗D�ꂽ������p�� |
Wallin |
|
1971 |
���{�������������� |
|
|
| IMV�J�� |
|
|
1971�� |
NLA �ϖ@���p�����n�߂� |
|
|
|
|
|
|
1972 |
�G���t��������T�������J�n |
|
|
| 1973 |
Laryngeal Mask �̔��� |
A. Brain |
|
|
|
|
|
| Sevoflurane, Isoflurane�@�̗Տ����p |
|
|
|
|
|
|
| �č��ŃG���t�������ĕ]�����ꔭ�� |
Dobkin |
|
|
|
|
|
| �G�� Critical Care Medicine �n�� |
|
 |
|
|
|
|
| 1975 |
�C�\�t�������Տ������J�n |
|
|
|
|
|
|
| American Society of regional Anesthesia �ݗ� |
|
|
|
|
|
|
| 1976 |
�Z�{�t�������č��ő�T�������J�n |
|
|
|
|
|
|
| �~�_�]�����J������� |
Walser |
|
|
|
|
|
| �G�� Regional Anesthesia �n�� |
|
|
|
|
|
|
| 1979 |
�L���x�N���j�E���Տ����p |
|
|
|
|
|
|
|
�G�� Anesthesia and Analgesia, Current Reseaches �� Anesthesia and Analgesia
�ƂȂ� |
|
|
|
|
|
|
| 1980 |
�C�\�t������FDA�̋����� |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1981 |
�G���t�������s�� |
|
|
|
|
|
|
���{�Տ������w��ݗ��A�w��@�֎��u���{�Տ������w��v�n�� |
|
|
|
|
|
|
1983 |
�ېΐ��� Traverol Laboratories, Inc. ���Z�{�t�������̊J�������擾 |
|
|
| 1984 |
�哤����n�}�Ƃ����v���|�t�H�[���̓��� |
|
|
|
|
|
|
| 1985 |
Anesthesia Patient Safety Foundation �ݗ� |
|
|
1985 |
�C�\�t��������T�������J�n |
�R�� �G�v�� |
|
|
|
|
|
1985 |
 |
�@�Z�{�t��������T�������J�n�B�z��������̗Տ��ł̗L�p�������{�ɂ����ďؖ����ꂽ�n�߂ẴP�[�X�ł��� |
|
�r�c �a�V�� |
�l����ȑ�w |
| 1986 |
Foundation for Anesthesia Education and research �ݗ� |
|
|
|
|
|
|
| 1987 |
�f�X�t�����̗L�p���̕� |
Eger |
|
1987 |
���{�����w��@�֎� Journal of Anesthesia �n�� |
|
|
| 1989 |
�v���|�t�H�[���Տ��g�p�J�n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1990 |
�C�\�t���������� |
|
|
|
|
|
|
�Z�{�t���������� |
�ېΐ��� |
|
| 1992 |
�f�X�t�������Տ��g�p�J�n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1995 |
�v���|�t�H�[���Տ��g�p�J�n |
|
|